登山シーズンはいつからいつまで?
毎年同じではなく、さらにルートによっても異なります。
今年の場合
・富士宮、御殿場、須走ルート:7月10日~9月10日
・吉田ルート:7月1日から9月10日
富士山の状況(残雪など)により、登山道の部分的な通行制限があったり、山小屋の営業が遅れたりする場合もあります。登山前には、必ず情報収集しておきましょう。
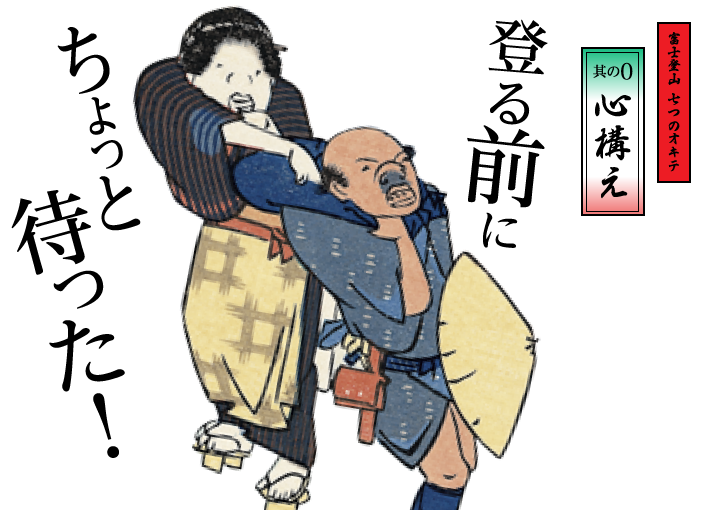
富士山では、高山病にかかる登山者が多くいます。これは、山小屋に宿泊せずに夜通しで登山し、山頂で御来光を拝むことを目的とする弾丸登山や、日帰り登山など、短時間で一気に高度を上げたことが原因です。寝不足のままで登山をすると、疲労がたまりケガにいたる場合もあります。安全な登山を楽しむために途中で1泊するような、ゆとりのある登山スケジュールを心がけてください。そして、自分の体調に合わせ、過信せず、無理のない準備と計画をお願いします。
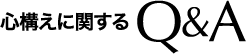
今年の場合
・富士宮、御殿場、須走ルート:7月10日~9月10日
・吉田ルート:7月1日から9月10日
富士山の状況(残雪など)により、登山道の部分的な通行制限があったり、山小屋の営業が遅れたりする場合もあります。登山前には、必ず情報収集しておきましょう。
■「1泊2日」スタンダードコース
山小屋のある七合目か八合目 → 山小屋で仮眠をとる → 翌朝(未明)に登頂、ご来光を拝む → お鉢めぐり → 下山
■「1泊2日」ぐっすりコース
山小屋のある七合目か八合目 →山小屋で睡眠をとる →翌朝、山小屋前でご来光を拝む →頂上へ →下山
※週末は混雑が予想され、山小屋の予約が取れない可能性があります。無理をしないためにも、平日に登りましょう。
近所を散歩するような歩き方では、すぐに息切れしてしまいます。呼吸が乱れず、心臓がドキドキしないようなペースを守りましょう。亀のような歩き方が基本です。疲れがたまりにくく、しかも身体が自然に高度順応することもできます。
富士山の登山道は、火山礫と小石がごろごろ。大股で歩いたり、かかとを上げて登ったりすると、足がすべりやすくなります。バランスが崩れると体力が奪われ、歩くたびに疲れがたまるので注意しましょう。歩幅を小さく、靴全体で踏みしめて歩くことが、結果早く登ることになります。
休憩時間は、自分の体調によって変えましょう。オーバーペース気味で息が荒くなってきたら、立ったままでいいので1〜2分休むのがコツです。5分以上の長めの休憩をとるときは、水分やエネルギーの補給、トイレに行ったり、ストレッチするなど有効的に使います。
標高が高くなると大気中の酸素濃度が低下して、体内の酸素が欠乏します。この酸欠が原因で起こることを総称したのが「高山病」なのです。
登山者によりさまざまですが、疲労感・脱力感・頭痛等が症状です。酸欠で体内のバランスが崩れ、脱水から循環機能に異常が生じると、ひどい場合は脳浮腫や脳水腫を発症し、命を落とすこともあるので、軽くみないでください。
弾丸登山や日帰り登山は、体力的に厳しいので高山病にかかる可能性が高くなります。山小屋に1泊以上宿泊するといった余裕のあるスケジュールで、登山をしましょう。また、登山前日には十分に睡眠をとり、飲酒も控えることも予防になります。
登山前、五合目で1~2時間ほど休憩をしましょう。こうすることで体が高度に慣れ、高山病にかかりにくくなります。
話ができる程度のゆっくりとしたペースで歩きましょう。話をしながら登山することで、自然と呼吸が確保されます。また、定期的な休憩を取り体力を維持することも、高山病対策のひとつ。25分登って5分休憩、50分登って10分休憩などが目安です。
登山中は、頻繁に水分を補給しましょう。水分を多く取って排尿することで、新陳代謝が活発になり、高山病にかかりにくくなります。トイレが近くなるからといって、水分を補給しない登り方は危険です。
お腹からしっかりと息を吐き出す腹式呼吸により、酸素を体内に多く取り入れましょう。腹式呼吸はまた、精神の安定、血圧の上昇を抑制、脳の活性化等への効果が高いといわれています。
命にかかわる場合があるので、早めに下山しましょう。