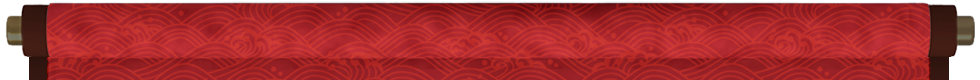富士登山に必要な基礎知識と心構え
まずは登山(とざん)の練習(れんしゅう)をしよう!

富士登山(とざん)の前に、近所(きんじょ)の山に登(のぼ)ってみましょう。静岡県内(しずおかけんない)には、浜石岳(はまいしだけ)や金時山(きんときやま)など、すてきな山がたくさんありますよ。
事前(じぜん)の準備(じゅんび)をしっかりしよう!

富士山には、4つの登山道(とざんどう)があります。体力(たいりょく)や日程(にってい)に合わせて、どのルートから登(のぼ)るのかじっくり検討(けんとう)してください。
リュックサック、雨具(あまぐ)、帽子(ぼうし)、手袋(てぶくろ)、着替(きが)え、水、食べ物、ヘルメット、マスクなど、事前(じぜん)の準備(じゅんび)をしっかりしておきましょう。
【写真提供】株式会社モンベル
高山病(こうざんびょう)に注意(ちゅうい)!
2,000m以上(いじょう)の高山(こうざん)では、高山病(こうざんびょう)という病気(びょうき)にかかりやすくなります。
高山病(こうざんびょう)というのは、頭(あたま)が痛(いた)くなったり、体がだるくなり食欲(しょくよく)がなくなったり、気持(きも)ちが悪(わる)くなって吐(は)いてしまう病気(びょうき)です。高山病(こうざんびょう)がひどくなると、動(うご)けなくなり、最悪(さいあく)の場合(ばあい)には、亡(な)くなってしまう方(かた)もいます。
12歳(さい)以下(いか)の子どもの場合(ばあい)、半数以上(はんすういじょう)が富士山で高山病(こうざんびょう)にかかるといわれています(日本旅行医学会の調査より)。
高山病(こうざんびょう)の症状(しょうじょう)が出たら、それ以上(いじょう)高い地点(ちてん)に上がらない、少し休(やす)んでも症状(しょうじょう)が良(よ)くならなければ山から下りる、ということを必(かなら)ず守(まも)ってください。
水分をしっかり取(と)りましょう!

登山中(とざんちゅう)はたくさん汗(あせ)をかきます。高山病(こうざんびょう)予防(よぼう)のためにも、こまめに水分(すいぶん)補給(ほきゅう)をしましょう。
【写真提供】株式会社モンベル
栄養(えいよう)補給(ほきゅう)をしましょう!

山(とざん)には体力(たいりょく)が必要(ひつよう)です。へたばって動(うご)けなくなってしまわないように、休憩(きゅうけい)する時(とき)には、パンやおにぎり、あめ、チョコレートなどで、しっかり栄養(えいよう)を補(おぎな)いましょう。
トイレに行きましょう!

おしっこをがまんすると、高山病(こうざんびょう)にかかりやすくなります。富士山の中には、トイレが少ないので、「山小屋(やまごや)を見たら、トイレに行(い)く」ことを心がけましょう。山小屋(やまごや)のトイレを使(つか)う場合(ばあい)は、200円~300円のトイレチップが必要(ひつよう)です。小銭(こぜに)の準備(じゅんび)も忘(わす)れずに。
ゆっくりとした計画(けいかく)をたてましょう。

無理(むり)な登山(とざん)をすると高山病(こうざんびょう)にかかりやすくなります。空気(くうき)の薄(うす)い富士山の環境(かんきょう)になれるためにも、山小屋(やまごや)に1泊(ぱく)以上(いじょう)して、ゆっくり登山(とざん)しましょう。山小屋(やまごや)へ事前(じぜん)に予約(よやく)することも忘(わす)れずに。
寒(さむ)さ対策(たいさく)は万全(ばんぜん)に!

富士山は、標高(ひょうこう)が高いので、真夏(まなつ)でも朝晩(あさばん)や、お天気(てんき)の悪(わる)い日はとても寒(さむ)くなります。
また、山頂(さんちょう)は、風が強(つよ)く、気温(きおん)が低(ひく)いため、寒(さむ)すぎて動(うご)けなくなくなってしまうこともあります。寒(さむ)さ対策(たいさく)は万全(ばんぜん)に。
【写真提供】株式会社モンベル